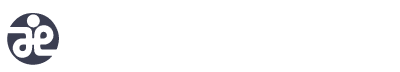ボランティア勉強会 第40弾「人と人をつなぐ 傾聴の力」

ボランティアセンターでは、年に3~4回、ボランティア活動の活性化を目的として、登録ボランティアグループを対象にボランティア勉強会を開催しています。
<今回のテーマ>
ボランティア勉強会 第40弾「人と人をつなぐ 傾聴の力」
9月8日(月)にふれあいセンター3階大会議室で開催し、傾聴に興味のある40名が参加しました。
皆さんは「傾聴」という言葉を聞いたことがありますか?ただ漠然と話を「聞く」とは違い、相手に耳、目、心を向けて「聴く」、相手を受け止め、共感し、心の負担が少しでも軽くなるよう手助けをするコミュニケーションの技法です。
今回は講師に一宮市で長年傾聴ボランティアの活動を続けていらっしゃる傾聴ボランティア「みみの木」代表 早川一枝 氏を招き、傾聴の心構えや基本、コミュニケーションの取り方などについて詳しくお話いただきました。

早川氏は傾聴ボランティア「みみの木」の代表として、多くの会員と共に傾聴ボランティア活動を続けるかたわら、他市などでも講座の講師等をされてみえるそうです。
今年で発足20年、会員数100名弱。
【傾聴ボランティア活動】
①個人宅訪問 約20か所月1~2回訪問
②施設訪問 約24か所の施設に1時間の傾聴を月2回程度 ※グループ・個人傾聴
③みんなの傾聴「まちかどサロン」月1回 ※どなたでも可
相手の話を聴いているつもりでも、つい口を出してアドバイスをしたり、「でも」と言ってしまったりすることがあると思います。しかし、傾聴するためには、相手の方が主人公だという謙虚な気持ちを持つことが大切だとわかりました。
講演の最後には、自己肯定感を高めるワークを行いました。


まず自分をほめる言葉を10個書いたあと、2人一組になり書かれた用紙を交換して、会話の最初に相手の名前を言ってから心を込めて10個の内容を伝える、というものです。
皆さん最初は少し恥ずかしそうにしていましたが、終わりには笑顔がこぼれていました。
◆ 参加者からの声(一部)
● 傾聴と一言で簡単に伝えていたが、目、耳、心で聴く。なるほどと思うことが多かった。
● 自分は人の話を聴いているようで、「でもね」と話を途中で切ってしまっていることに気付きました。
● 特に家族の中で、傾聴を心がけたい。身内だからこそ、いい加減になるので。
● 傾聴ボランティアをしていますが、今日のお話でこれからも頑張ろうと思います。
本日勉強した内容を、団体内でのコミュニケーションやボランティア活動に活かしていただけたらと思います。
今後もボランティアの皆さんの活動に活かせるように、様々なテーマで開催を計画しています。
皆さまのまたのご参加をお待ちしています。
(VC 岡)